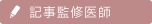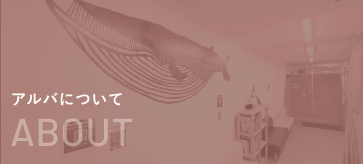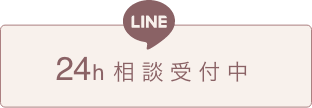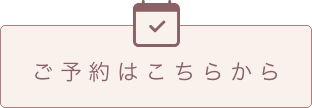エビアレルギーが心配な方へ

はじめに
エビ(甲殻類)アレルギーは大人に多い食物アレルギーの一つで、症状や原因にも様々なパターンがあります。
中には生のエビだけに反応する人や、加熱したエビだけで症状が出る人、さらには特定の種類のエビ(例:バナメイエビ)に限ってアレルギー反応を起こすケースも報告されています。
1. エビを食べてしまったら、怖い
「エビって、天ぷらでもパスタでもおいしいのに、ちょっとでも食べたら肌がかゆくなったり、息苦しくなったりするかもしれない…。食べてしまうのが怖い」
「外食するとき、いちいち店員さんに“エビは入っていませんか?”って聞くのが申し訳ないし、周りにも気をつかわせてしまう。もっと気軽に食事を楽しみたいのに…」
エビアレルギーを持っていると、こんなふうに日常生活のあらゆるシーンで不安がつきまといますよね。
コンビニのお弁当を選ぶときでさえ、「このソース、もしかしてエビ由来の成分が入っているかも…?」なんて気にしなくてはいけません。
実は、「甲殻類」(エビやカニなど)にアレルギーがある人は、意外と少なくありません。
アレルギーとひと口に言っても症状の重さは人それぞれで、「エビをちょっと触るだけで手がかゆくなる」という方もいれば、「まったく食べられないけど、調理のにおいぐらいなら平気」という方もいます。
どのパターンでも、不安は不安ですよね。
そこで、ここではエビアレルギーの原因、病院での検査方法、誤食したときの対処法、そして外食や料理の工夫などをまとめてみました。
「少しでも心配が軽くなる」「安心して生活できる」きっかけになればうれしいです。
2. エビアレルギーって何?原因と発症のしくみ
(1)アレルギー反応ってなに?
アレルギーとは、体の免疫機能が食べ物や花粉などを“敵”と勘違いして過剰に反応してしまう状態をいいます。
本来は体を守るはずの免疫が、「これは危険なものだ!」と誤作動を起こし、くしゃみやじんましんなどの症状を引き起こしてしまうのです。
(2)エビの場合は?
エビの身や殻に含まれるタンパク質(細かい名前は省きますが)が、体質によっては“敵”とみなされることがあります。
食べたり触ったりしたときに体内で警報が鳴り、肌荒れやかゆみ、呼吸の苦しさなどの症状を引き起こします。
また、エビとカニやロブスターは同じ「甲殻類」に分類されるため、どちらかにアレルギーがある人はもう片方でも症状が出ることは約70%とされていますが、実際にはどちらかだけの方が多いです。
もちろん個人差があり、「エビはNG、カニは平気」という方もいれば、その逆のケースもあります。
エビアレルギーを持つ場合、他の甲殻類や関連する食物にも注意が必要です。
実際、甲殻類(エビ・カニ)と軟体動物(イカ・タコ・貝類)の交差反応は20%程度と報告されており、エビアレルギーだからといって必ず貝類もダメになるわけではありません。
筆者の臨床経験でも、エビとイカの両方にアレルギーがある人は非常に稀です
エビアレルギーだからといって貝やイカ・タコまで一律に除去する必要はなく、個別に食べられるかどうか確認することが推奨されます
(3)大人になって急に出ることは普通
「子どものころは食べられたのに、大人になってから急にエビを食べると調子が悪くなる」という方もいます。
これが普通で、アレルギーは、ある日突然発症することがあります。
逆に子どものころはダメだったのが、大人になって症状が軽くなることもあります。
いずれにせよ、一度「エビを食べると変だな」と感じたなら、きちんと対策を考えた方が安心ですよね。
3. エビアレルギーのいちばん怖いところ
このため通常は、生でも加熱後でもエビを食べればアレルギー反応がおきます。
しかし、一部の人では生のエビを食べたときにのみ症状が出て、加熱したエビは食べられたり、逆にごく稀ですが、生のエビは大丈夫でも加熱したエビでだけ症状が出るということもあります。
とはいえ大多数のエビアレルギー患者では、生でも加熱後でも関係なく症状が現れる点は押さえておきましょう。
なので、エビアレルギーの困るポイントは、「気づかないうちに口にしてしまったらどうしよう」という不安ではないでしょうか。
調味料やだし、スナック菓子など「エビが入っていそうに見えないもの」にも、実はエビの粉末やエキスが混ざっていることがあるからです。
- 例1:春巻きや餃子の具材にエビが少し入っている
- 例2:和風だしやソースにエビ由来の成分が使用されている
- 例3:フライを揚げる油が共通で、エビの成分が他の揚げ物に移ってしまう
こうした場合、ちょっとした量でもアレルギー反応が出てしまう人もいれば、ある程度の量を食べて初めて具合が悪くなる人もいますが、ほとんどの場合では同じ調理場程度では症状はでません。
ただ、一度症状が強く出るようになると、今後ますます注意しなければいけません。
知らずに食べてしまって、息苦しくなったり倒れてしまったりしたら…と考えると、外食するのも怖くなりますよね。
4. クリニックでできる診断・検査の詳細
「エビを食べると毎回調子が悪い気がするけど、本当にアレルギーなのかな?」と迷っているなら、一度クリニックで検査してもらうのがおすすめです。
病院やクリニックでは、いくつかの方法でアレルギーの有無や重症度を調べてくれます。
-
問診
まずは「いつどんな状況でエビを食べて、どんな症状が出たか」を医師が聞き取ります。これだけでも、かなりアレルギーの可能性を絞り込めることがあります。
-
血液を調べる方法
採血をして、その中にエビに反応する成分がどれくらい含まれているかを調べます。数値が高いほどアレルギーの疑いが強まりますが、甲殻類の場合、実際には症状があるにも関わらず採血の値が低い人の方が症状が強くでます。個人差もあるので最終判断は医師が総合的に行います。
-
実際に少しずつ食べる負荷テスト(食物負荷試験)
これは医師の監督のもと、実際に食べてみる検査です。本当にエビが原因か、どれくらい食べると症状が出るのかを厳密に確認します。リスクが高いので、基本的にはクリニックや病院で実施しますが、確定診断をするには一番確実な方法です。
「検査って痛そう」「面倒くさそう」と身構える方もいますが、最近の医療現場では患者さんの負担や不安を減らすため、できるだけ簡便な方法で済むよう工夫してくれます。
はっきりと「あなたの場合はここまで大丈夫、ここからはやめておいた方がいい」とわかると、今後の生活がずいぶん楽になるはず。とりあえず相談だけでもしてみると、気持ちが軽くなりますよ。
5. 誤食した場合の具体的な対処法
「もしうっかり食べてしまった!」そんなときに知っておきたい基本の行動を、もう少し詳しく見ていきましょう。
- まずは落ち着いて症状をチェック
口の周りがかゆい、唇が少し腫れている程度なら、すぐに大騒ぎしなくても大丈夫なケースが多いです。ただし油断は禁物。徐々に悪化することもあるので、誰かにそばにいてもらうか、すぐ連絡できるようにしておきましょう。 - 苦しくなってきたら迷わず助けを呼ぶ
息がしづらい、喉がイガイガして声が出しにくい、全身にじんましんが広がってきた…といった症状が出たら、我慢せずに救急車を呼ぶか、周りに「救急に連絡して」と伝えてください。下手に「少し休めば大丈夫かも」などと思っていると、取り返しのつかない状態になるかもしれません。 - 処方された注射薬(自己注射)を持っている場合は使う
過去に症状が重かった方は、あらかじめ医師から応急処置用の注射薬(エピペン)を処方されていることがあります。苦しくなってきたら、周囲に手伝ってもらいながらすぐに注射を打ちましょう。打ったあと症状が収まっても、必ず病院で診てもらってください。 - 特に子どもの場合は周囲のサポートが必須
お子さんがアレルギーを持っている場合は、本人が自覚できなかったり、うまく説明できないこともあります。給食や外食で勝手にエビ料理に手を出してしまうリスクもあるので、事前に学校や習い事の先生、友達の親御さんなど、周囲の大人に協力をお願いしておくと安心です。「こういう症状が出たら、すぐに救急車を呼んでほしい」と具体的に伝えておきましょう。
6. 外食時の注意点と避けたい料理リスト
エビアレルギーの方が外食を楽しむためには、事前の一言確認とエビ入り料理の傾向を知ることがポイントです。
(1)お店の人に伝える
- そもそも外食自体がリスクですが、注文するときに「エビアレルギーなんです」とと伝えてしまいましょう。店員さんが「こちらのソースにはエビ成分が入っています」「フライの油が共通です」など教えてくれることがあります。
- 遠慮して黙っていると、結果的に自分が苦しむだけではなく、お店側にもトラブルになる可能性が。恥ずかしがらず言ってしまった方が、みんなハッピーです。
(2)要注意メニュー・料理の例
一番誤食しやすいのは、スープとラーメンです。
- 中華料理の海鮮炒めや餃子、春巻き:小さく刻んだエビが入っていることが多い。
- 和食の出汁(だし):実は海老で味を出しているケースもある。かき揚げに細かくエビが混ざっている場合も要チェック。
- 揚げ物全般:エビフライと同じ油で唐揚げや天ぷらを揚げていることがあり、油を通じてエビ成分が入り込む可能性が。
- スナック菓子:海老のパウダーが風味付けに使われている場合がある。見た目はエビっぽくなくても、裏の原材料表示を見ると「えび粉末」など書いてあることが。
- パスタソースやピザ:トマトベースやクリームソースに海老を細かく入れるレシピも多いため、メニューに「魚介」や「シーフード」と書かれているものは注意。
(3)店選びの工夫
- エビ料理が看板メニューのお店は避けるのが無難。
- ファストフードやチェーン店の場合、アレルゲン情報を公式サイトに載せているケースが多いので、事前にチェックすると安心。
- ビュッフェスタイルやフードコートでは、いろいろな料理が並んでいて、混ざりやすい点に注意。トングやスプーンを共用している場合、エビ料理のトングで他の料理を取ると微量混入のリスクがあります。
7. 代替食品の紹介(エビなしで作れる料理の工夫)
「エビのプリプリした食感や旨味が好きだったのに、もう食べられないなんて…」とガッカリしている方もいるかもしれません。
でも、最近はエビに似た味や食感を出す食材や加工食品がいろいろあります。ちょっとしたアイデア次第で満足度の高い料理を楽しめるはずです。
- エビの代わりに魚のすり身
お好み焼きやかき揚げなどでエビの代わりに白身魚のすり身(はんぺん、ちくわなど)を刻んで加えると、かみごたえやうま味がアップします。 - 鶏肉や豚肉を小さめにカットする
実は、小さめにカットした鶏肉や豚肉をエビ風に下味を付けると、プリッとした食感を楽しめるレシピもあります(例えば片栗粉をまぶして焼くなど)。 - 市販の「えび風味なし」フライや餃子
最近は冷凍食品などで「エビの代わりに魚介を使っている商品」や「そもそも甲殻類を使っていない商品」を選ぶだけで、エビが入っていないのに似たような満足感を得られるものが増えています。原材料表示をチェックして、エビ不使用の代替品を活用してみるのも手。 - ダシやソースを工夫する
エビ由来のだしが欲しいときは、昆布やかつおぶし、椎茸などをうまく組み合わせることでコクを出すことができます。トマトや玉ねぎ、にんにくなどをじっくり炒めて旨味を引き出すソースを作れば、エビに負けない深みのある味わいになります。
「エビなしでこんなにおいしく作れるんだ!」という発見があると、料理の幅が広がり、「意外と大丈夫かも!」と思えるようになるはずです。
8. エビアレルギーと上手に付き合おう
ここまで、エビアレルギーの原因や検査方法、誤食したときの対処法、外食での注意ポイント、代替食品のアイデアなどをお伝えしました。
エビアレルギーを持つと、どうしても「うっかり食べたらどうしよう…」という不安が消えませんが、正しい知識を身につけ、周囲にも協力を仰ぎ、そして日々ちょっとした工夫を重ねることで、不安を大幅に減らせるはずです。
おさらいポイント
- まずはクリニックでチェック
- 怪しいなと思ったら、軽い気持ちで受診。血液検査や肌の反応テストなどで、エビアレルギーかどうか確かめましょう。
- 誤食が怖いなら対処法を身につける
- 症状の出方は人それぞれ。軽ければ様子見でも、呼吸がしづらいなど重い症状が出たら迷わず救急。応急用の注射薬がもらえる場合もあるので、医師に相談を。
- 外食や食品選びを慎重に
- 「エビアレルギーです」とお店の人に伝える、パッケージの表示を必ずチェックするなどを習慣に。特にソースや出汁、揚げ油などに注意。
- 代わりの食材や工夫を楽しむ
- 小さくカットしたお肉や魚のすり身など、エビの代わりになる食感を再現するレシピをいろいろ試すと、新たな発見があります。
- 周りに伝えて協力してもらう
- 家族や職場、学校などに「私(うちの子)はエビがダメなんだ」と共有しておくだけでも、いざというときの手助けが大きく変わります。
「エビアレルギーって本当に厄介」「もう外食は楽しめない」と落ち込みがちかもしれません。けれど、実際にアレルギーを持ちながらも、うまく対策して家族や友だちと楽しく食事をしている人は大勢います。
大事なのは、自分の体としっかり向き合うこと。たとえアレルギーがあっても、悲観しすぎず、でも過信もせず、バランスよく「安全策をとりながら日々を満喫する」ことを目指しましょう。
もし「検査を受けたいけど、どこに行けばいいかわからない」と思ったら、身近な内科や皮膚科などにまず相談してみてもいいですし、アレルギーを標榜しているクリニックを探してもOKです。「ひょっとして…」と思ったら、ひとりで悩まずに病院を頼ってみるのが一番の近道ですよ。
最後に
エビアレルギーは、確かに注意が必要な食物アレルギーのひとつです。
でも、正しい理解とちょっとした工夫があれば、過度に怖がりすぎずに日常生活を送ることができます。
むしろ「エビが使えないからこそ、ほかの食材でおいしい料理を作ろう!」といった新しい楽しみ方を見つけられるかもしれません。