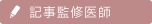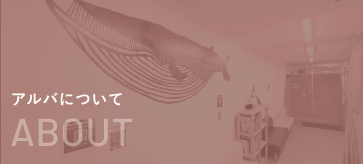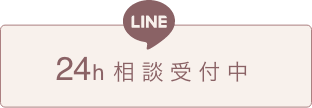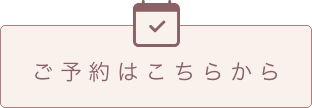キウイアレルギーかなと思ったら?
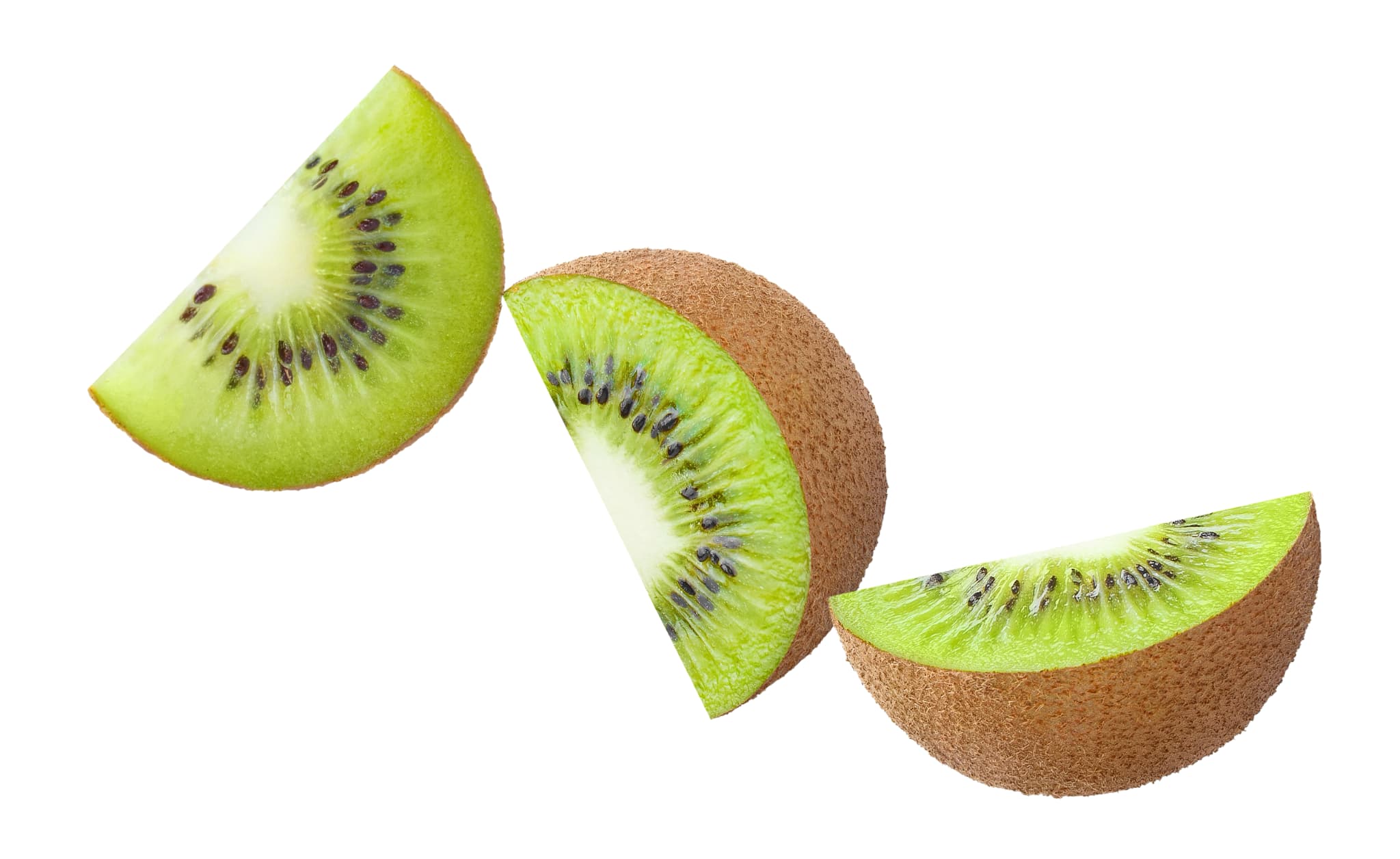
キウイアレルギーでお悩みの方へ。
症状を放置するリスクと安全な解決方法を解説します。
「子どもに初めてキウイを食べさせたら、口の周りが赤くなってしまった…」
「私自身、キウイを食べると喉がイガイガして不快だけど、これって放置しても大丈夫?」
「キウイアレルギーがある場合、他の果物も食べられなくなるのか心配…」
お子様の食物アレルギーを心配されるお母様や、ご自身の食物アレルギーの症状で悩む方から、このような不安の声をよく伺います。
特にキウイアレルギーは最近増えているにもかかわらず、正しい知識が浸透していないのが現状です。
こうした不安を感じるのは、ごく自然なことです。
「ただの軽い症状」と放置していませんか?
「症状が軽いから病院に行くほどじゃない」と考える方も多いかもしれません。
しかし、アレルギー反応は軽い症状から急激に重篤な症状へ進行することがあります。
特にお子様の場合、初めての摂取でも約40%が全身症状を伴うことが報告されています。
もし、「軽い口の痒みだから」と放置してしまうと、ある日突然呼吸困難や意識低下など、命に関わる重篤な症状が起きる可能性も否定できません。
🔍 わかりやすく説明すると…
● 小さいお子さんに多いタイプのアレルギー(一次感作)
-
キウイを初めて食べたときに、腸からアレルギー反応が始まるタイプです。
-
キウイに含まれる「Act d 1」や「LTP」というたんぱく質が原因になりやすく、全身にじんましんが出たり、呼吸が苦しくなったりする強い症状が出ることがあります。
-
特に初めてキウイを食べた直後に症状が出たお子さんは、このタイプの可能性が高いです。
● 大人に多いタイプのアレルギー(二次感作)
-
もともと花粉症がある方に多いタイプで、体が「花粉」と「キウイ」を似たものと勘違いして反応します。
-
これは「PR-10」や「プロフィリン」といったたんぱく質が関係していて、キウイを食べたときに口の中がピリピリしたり、喉がかゆくなったりする『口腔アレルギー症候群(OAS)』という軽い症状が多いです。
-
このタイプは、リンゴ・モモ・ナシなど他の果物にも似た反応が出ることがあります。
症状別頻度
| 症状カテゴリ | 小児 (%) | 成人 (%) |
|---|---|---|
| 口のかゆみ | 54 | 62–97 |
| 皮膚(蕁麻疹・血管浮腫) | 38–56 | 22–38 |
| 消化器(腹痛・嘔吐) | 21 | 17–20 |
| 呼吸器(喘鳴・呼吸困難) | 8–18 | 8–18 |
| アナフィラキシー | 38–40 | 12–18(ICU 入院例<2%) |
出典:Moreno 2015, Lucas 2004, Thermo Fisher
✅ 要点まとめ
-
重症率は小児が約2倍。40%前後がアナフィラキシー症状。
-
成人は口のかゆみ主体で 6–10人に1人が全身化。
-
背景には 一次消化管 vs 花粉交差 の感作経路差。
-
臨床では 小児は初回でも症状によってエピネフリン準備、成人は 花粉症対策 が肝要。
放置するリスク、知っていますか?
アレルギー症状は、軽度のうちは「口の中がピリピリする」「口の周りが赤くなる」といったものが一般的ですが、放置すると、次のような重大な症状を起こすこともあります。
-
突然の重症化(呼吸困難や血圧低下などアナフィラキシー症状)
-
食べられるものが限定され、栄養バランスが崩れる
-
心理的ストレスが強まり、食への不安感が増す
特に小児の場合、大人よりも全身症状を伴うケースが多いため、早めの適切な対処が必要です。
キウイの品種による症状の違い
キウイアレルギーには、緑キウイとゴールドキウイで症状の出方や重症度に違いがあることをご存じでしょうか?
特に緑キウイはアナフィラキシーのリスクが高く、症状が重篤化しやすい傾向があります。
キウイにはいくつかの品種がありますが、特に一般的な「グリーンキウイ」と「ゴールドキウイ」ではアレルギー症状の出方が大きく異なります。
グリーンキウイ(ヘイワード)

- 代表的な緑肉種で、酸味が強く、一般的なキウイとしてスーパーなどで多く販売されています。
- アレルゲン数が多く、特に「Act d 1」という消化管感作に関連するタンパク質が含まれています。
- 症状が強く現れやすく、アナフィラキシーなどの重症反応が起こりやすい傾向があります。
- 生のままだけでなく、缶詰など加熱処理をした場合でもアレルゲンが残りやすいことが特徴です。
ゴールドキウイ

- 黄肉種で、甘みが強く、近年人気が高まっています。
- アレルゲンの種類が比較的少なく、症状も緑キウイより軽いことが多いとされています。
- 軽い口腔内の痒みやイガイガ感(口腔アレルギー症候群:OAS)が主体で、全身症状は少ない傾向があります。
ただし、どちらのキウイもアレルゲンとして「熱に強いアレルギー成分」を含むため、完全に安全とは言えません。
| 緑キウイ | ゴールドキウイ | |
|---|---|---|
| 口腔内掻痒 | 多い | やや少ない |
| アナフィラキシー率 | 高い | 低い |
| 加熱によるアレルゲン低下 | 一部は残存 | 不明 |
| 症状出現時間 | 即時型 | 同等かやや遅延傾向 |
✅ 要点まとめ
-
グリーンキウイ(ヘイワード)はアレルゲンが多く、重症化リスクが高い
-
ゴールドキウイはアレルゲンが少なく、比較的軽症にとどまる傾向
-
アナフィラキシー歴のある方では両方完全除去が基本
✅ 医者向け
主なキウイの品種と特徴
| 品種 | 学名 | 色・味 | 市場例 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ヘイワード(緑) | Actinidia deliciosa | 緑肉・酸味強い | スーパーに多い | アレルゲン数が最多(13種) |
| ゴールド(黄) | A. chinensis | 黄色・甘い | ゼスプリ・サンゴールドなど | アレルゲン少ない(3–4種) |
| レッド | A. melanandra など交配種 | 赤芯・香り強い | 高級品・限定販売 | データ乏しいが Act d 1 存在 |
アレルゲン構成の違い(分子レベル)
| アレルゲン | 緑キウイ (A. deliciosa) | ゴールドキウイ (A. chinensis) | 機能 |
|---|---|---|---|
| Act d 1 | ✔ | ✔ | システインプロテアーゼ、消化管感作に関与(高リスク) |
| Act d 2 | ✔ | ❌ | サーモチン様タンパク |
| Act d 5, 11 | ✔ | ❌ | プロフィリンなど、交差抗原性あり |
| Act d 8 | ✔ | ✔ | PR‑10、花粉症との交差反応(OAS) |
| Act c 1 | ― | ✔ | ゴールド専用(Act d 1 相同) |
研究ポイント:
-
-
ゴールドキウイは全体的にアレルゲン数が少ない → 重症化リスクは理論上低い可能性(ただしAct d 1は含むため、完全に安心ではない)【Asero 2014, Lucas 2004】
-
Act d 1 は加熱耐性+消化酵素耐性 → 生でも缶詰でも残存しやすい主要アレルゲン
-
花粉症との関連性について
キウイアレルギーと花粉症の関連には、分子レベルでの「交差反応」が深く関与しています。これは、ある物質に対する免疫反応が、似た構造を持つ別の物質にも反応してしまう現象です。
特に有名なのが、シラカバ(Birch)やハンノキ(Alder)などの花粉に含まれるPR-10というタンパク質と、キウイに含まれるAct d 8というアレルゲンの交差反応です。このため、春先に花粉症を発症する方が、キウイを食べたときに口や喉にかゆみを感じる「口腔アレルギー症候群(OAS)」を発症することがあるのです。
具体的な関連例
- シラカバ花粉症を持つ方は、リンゴ、モモ、サクランボ、そしてキウイでOASを起こすことがある
- キウイに含まれるAct d 8は、花粉の主要アレルゲンであるBet v 1と類似しているため、体が間違って反応してしまう
花粉症との関連がある患者の特徴
- 成人に多く見られ、症状は比較的軽く、主に口腔内に限局します
- 季節性の花粉症と一致して症状が悪化するケースもあります
- 重篤なアナフィラキシーには至りにくいが、まれに全身反応を起こす場合もあるため油断は禁物です
花粉症持ちの方へのアドバイス
- 花粉症の診断がついている方で、生のキウイ摂取後に喉や唇がかゆくなるような場合は、早めにアレルギー専門医へ相談しましょう
- 花粉の飛散時期には交差反応が起こりやすくなるため、食物による症状が強く出ることがあります
- 花粉症とキウイアレルギーの両方が疑われる場合は、成分別アレルゲン検査(Component Resolved Diagnostics:CRD)で、原因アレルゲンを明確にすることが推奨されます
キウイアレルギーは花粉症との関連性も指摘されています。特にシラカバやハンノキなどの花粉症をお持ちの方は、「口腔アレルギー症候群(OAS)」という形でキウイにも反応しやすい傾向があります。これは、花粉とキウイに共通するアレルゲン(PR-10タンパク質)が原因となっています。そのため、花粉症の方でキウイを摂取した際に口の中や喉の痒みが現れる場合は、キウイアレルギーを疑う必要があります。
キウイアレルギーの対処法と予防について
キウイアレルギーがある方が安心して生活するために、次のような対策があります。
① 症状が出たときの対応(急な反応への備え)
-
呼吸が苦しくなったり、じんましんが急に広がるような強い症状が出た場合は、すぐに**アドレナリンの自己注射(エピペン)**を使い、救急受診が必要です。
-
軽い症状(口のかゆみ、少しの湿疹など)のときは、抗アレルギー薬やステロイドの内服で落ち着くこともあります。
🌟急な反応のために、薬や自己注射をあらかじめ用意しておくことが大切です。
② エピペンの持ち歩きについて
-
過去にアナフィラキシー(全身の重いアレルギー症状)を起こしたことがある方には、エピペンを常に持ち歩くようにお願いしています。
-
ご家族や学校の先生にも、使い方を知っておいてもらうことが大切です。
③ 食べ物の選び方(食事管理)
-
基本的に生のキウイや加熱していないキウイは避けるようにしましょう。
-
ただし、缶詰や加熱されたキウイ(コンポートなど)は、アレルゲンが弱くなるため、食べられる方もいます。
-
ある研究では、20人中15人の子どもが加熱済みキウイを安全に食べられました。
-
④ 他の食べ物や花粉にも注意が必要なことがあります
-
キウイに反応する方は、ラテックス(ゴム)や他の果物、花粉に対してもアレルギーがあることがあります。
-
すべてを避ける必要はありませんが、体調や反応を見ながら、一人ひとりに合った方法を相談しながら決めていきます。
アルバアレルギークリニック札幌での具体的な対応
当院でも、この最新の検査と細やかなカウンセリングを活用し、アレルギーに特化した診断・治療サービスを提供しています。
- 採血検査で症状の原因を明確化
- 経験豊富な専門医が診断結果をもとに安全な食生活をサポート
- 万が一の重症化に備えたアドレナリン自己注射(エピペン)の処方も対応
少しでも気になる症状があれば、ご相談ください。
キウイアレルギーについて、インスタグラムの動画でもお話ししていますので、ぜひご覧ください♪
https://www.instagram.com/reel/DM1pbgjReVD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
参考文献
-
Moreno Álvarez A, et al.
Kiwi allergy in children: characterisation of clinical features and molecular diagnosis.
Pediatric Allergy and Immunology. 2015;26(7):718–723.
https://doi.org/10.1111/pai.12451 -
Lucas JS, Lewis SA, Hourihane JO.
Kiwi fruit is a significant allergen and is associated with differing patterns of reactivity in children and adults.
Clinical & Experimental Allergy. 2004;34(7):1115–1121.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2004.01995.x -
Asero R, et al.
Component-resolved diagnosis of plant food allergy.
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. 2012;12(3):261–267.
https://doi.org/10.1097/ACI.0b013e3283536c38 -
Breiteneder H, Mills ENC.
Molecular properties of food allergens.
Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2005;115(1):14–23.
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.11.009 -
Le TM, van Hoffen E, van Reijsen FC, et al.
Component-resolved diagnostics: potential for replacement of food challenges.
Allergy. 2013;68(4):461–468.
https://doi.org/10.1111/all.12112 -
Thermo Fisher Scientific.
Allergen Encyclopedia – Act d 1 to Act d 11.
https://www.thermofisher.com/allergens (最終閲覧日: 2025年7月)