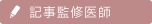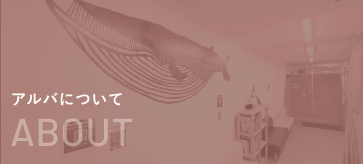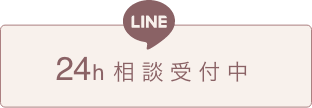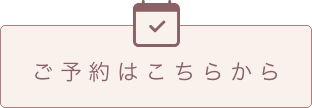トマトアレルギー

はじめに
トマトは料理に欠かせない食材のひとつですが、トマトに対するアレルギーを持つ方も少なくありません。
赤ちゃんから大人まで発症し得るこのトマトアレルギーは、多くの場合IgEを介する即時型アレルギー反応として現れます。
一方で、まれに接触皮膚炎や遅発型の腸症候群を引き起こす非IgE型も報告されており、一概に「食べるとかゆくなるだけ」とは言い切れません。
さらに、花粉症との関連に着目し、シラカバ・ヨモギ・ブタクサなどの花粉アレルゲンとの交差反応機序にも詳しく触れます。
「トマトを食べると口がイガイガする」「花粉症もあるけれど、どんな関係があるの?」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください
1.症状:軽度のOASからまれなアナフィラキシーまで
軽症:口腔アレルギー症候群(OAS)
トマトアレルギーで最も多いのは口腔内の症状です。生のトマトを食べた直後に、
-
唇や舌、喉のかゆみ・イガイガ感
-
口周辺の軽い発赤やヒリヒリ感
などが起こり、数分以内に治まるケースが典型的です。これは即時型(IgE介在性)の反応であり、加熱してあるトマト(トマトソース、ケチャップなど)では症状が出ない人も少なくありません。口周りにトマトの果汁がついた乳幼児が、一時的に赤くかぶれることもありますが、多くは時間とともに落ち着きます。
中等度:全身症状への広がり
一部の患者さんでは、口腔局所を超えて症状が全身に及ぶことがあります。たとえば
-
全身性のじんましん、皮膚の強いかゆみ
-
鼻づまりやくしゃみ、喉の違和感
-
軽度のぜん鳴、吐き気や腹痛などの消化器症状
トマトそのものを触っただけで接触蕁麻疹を起こす例や、さらにひどい湿疹へと悪化するケースも報告されています。特に小児では口周りに付着したトマト成分が刺激となり、真っ赤に腫れることがあります。
重症:アナフィラキシーもまれに
トマトアレルギーで命に関わるアナフィラキシーは比較的まれですが、あります。
呼吸困難、喉の腫れ、血圧低下など全身性のショック反応を起こす場合があり、迅速なエピネフリン(アドレナリン)の投与が必要です。
特に、
-
LTP(リピドトランスファープロテイン) という加熱に強いアレルゲン
-
食後の運動により増強される「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」
などでは、調理済みトマトでも症状が出たり、運動との組み合わせで重篤化したりします。
2.診断方法:皮膚プリックテスト・IgE検査・負荷試験
(1)問診が第一歩
診断においては、まず問診がとても大切です。以下を詳しく医師に伝えましょう。
-
トマトを食べた後、どのくらいの時間で症状が出るか
-
どんな症状(口腔内のみ、全身に及ぶか、皮膚か呼吸器かなど)
-
加熱品や少量なら食べられるか
-
花粉症やラテックスアレルギーの有無
-
食後に運動した時だけ重症化するかどうか
こうした情報で即時型か遅発型か、花粉症との交差の可能性、重症度などを予測します。
(2)皮膚プリックテスト(SPT)
トマト抽出エキスを皮膚に接触させ、その部位を軽く刺して反応を観察する方法です。生のトマト果肉を用いた「プリック・プリック法」も行われます。15分ほどで発赤や膨疹が出れば陽性ですが、花粉症との交差反応による偽陽性もよくあるため、結果の解釈は注意が必要です。
(3)特異的IgE抗体検査
血液中のトマト特異的IgEを測定し、アレルゲン感作の有無を調べます。こちらも交差反応性炭水化物決定基(CCD)や花粉に由来するIgEなどにより、偽陽性が起こりがちです。またトマトの分子レベルのアレルゲンコンポーネント(プロファイリン、PR-10、LTPなど)を詳しく調べる検査もあり、どのタンパクにIgEが反応しているかが分かると重症度の予測に役立つ場合があります。
(4)除去試験・食物負荷試験
-
除去試験:一定期間トマトを完全に除去し、症状が改善するかを見る。
-
食物負荷試験:入院または専門外来で少量からトマトを摂取して症状を観察。アナフィラキシーのリスクがあるため、安全管理体制が整った医療機関でのみ実施されます。
特に非IgE型(FPIESなど)が疑われる場合、皮膚テストやIgE検査が陰性でも、負荷試験で診断を確定することがあります。
3.治療・管理:回避が基本、花粉症が原因なら免疫療法も
(1)回避と工夫
多くの場合、トマトの摂取を避けることが第一の対策です。生のトマトを少量でも症状が出る方は厳格な除去が必要になります。スープやドレッシングなどに紛れ込んでいることもあるため、食品ラベルの確認や外食時の店員へのアナウンスを欠かさないようにしましょう。
一方、加熱によって症状が出にくくなる人もいます。これは主なアレルゲンタンパク(プロファイリンやPR-10)が熱に弱いからです。軽症の方なら、
-
皮をむく
-
完全に火を通す
などで口腔アレルギーを回避できる場合があります。ただしLTP感作の場合、加熱しても安心とは限らず重症症状を呈するケースもあるため、必ず医師の指導を受けましょう。
(2)薬物療法
-
抗ヒスタミン薬:口腔内や皮膚のかゆみを軽減する目的で用いられる。
-
エピペン(アドレナリン自己注射):過去に重症反応があった方や、LTP感作がある方などに処方される。症状が出たときは速やかに筋注し、医療機関を受診します。
-
吸入β刺激薬:喘息症状が強い場合は吸入剤を常備。
(3)免疫療法(減感作)
トマトアレルギー自体の経口免疫療法はまだ一般的ではありませんが、**花粉症が原因で二次的に起こるトマトアレルギー(PFAS)**に対しては、原因花粉への減感作療法が効果をもたらす可能性があります。たとえば日本の研究では、スギ花粉症に対する皮下免疫療法を行ったところ、トマト摂取時の症状が軽減したとの報告があります。シラカバ花粉やブタクサ花粉でも同様のメカニズムが想定され、PFAS全般への応用が期待されています。
(4)アナフィラキシー時の対応
アナフィラキシーを起こした場合、最優先はエピネフリン筋注です。さらに酸素投与、点滴、抗ヒスタミン薬やステロイドなどが必要に応じて行われます。食物依存性運動誘発アナフィラキシーの場合は運動を中止し、最低半日は安静を保つことが推奨されます。
4.発症メカニズム:IgE介在型が主体、まれに非IgE型も
大半は**即時型(タイプI)**で、トマト中のアレルゲンタンパクがIgE抗体と結合し、肥満細胞からヒスタミンなどが放出されることで症状が起こります。
中でも2つのルートが注目されており、
-
トマト自体で一次感作:LTPなど加熱耐性の強いアレルゲンが関与しやすく、地中海沿岸での重症例が多い。
-
花粉症からの二次感作:プロファイリン(Sol l 1)やPR-10(Sol l 4)などの交差反応を介して口腔アレルギー症候群を引き起こす。
一方、遅発型(タイプIV)の接触性皮膚炎やFPIES型など、非IgEまたは混合型もまれに存在します。また、トマトにはヒスタミン量が多いため、**アレルギーでなくても軽い口の違和感を覚える(偽アレルギー)**こともあるので注意が必要です。
5.疫学:南欧に多く、学童期以降で増える
地域差・年齢差
-
ヨーロッパ:1.5~16%と報告され、特に**南欧(イタリアやスペインなど)では多くの例がみられます。
-
アジア:甲殻類やソバなどのアレルギーが優勢で、トマトはトップアレルゲンではないものの、0.02~7.8%の幅で報告があります。
-
年齢差:花粉症の発症が増える学童期以降~成人で頻度が高く、乳幼児では少ない傾向。とはいえ、離乳食期の赤ちゃんが初めて食べて蕁麻疹を起こす例も一部報告されています。
他のアレルギーとの併存
トマトアレルギーの方は、アトピー性皮膚炎や喘息、他の食物アレルギー(ラテックスやバナナなど)を併発しているケースも多くみられます。特にイネ科花粉症児でトマト感作率が高いなど、花粉との関連が深いことが統計的にも示されています。
6.予防法:早期導入と花粉症対策
一次予防
特定の食物アレルギーを100%防ぐ確立した方法はありませんが、乳児期から多様な食材を適切に与えることでアレルギー発症リスクを下げる可能性があります。ピーナッツや卵などでエビデンスが示されており、トマトでも同様の考え方が推奨されます。アトピー体質の乳児でも無理にトマトを避ける必要はなく、湿疹ケアをしながら普通に離乳食として導入していくことが多いです。
二次予防
既にトマトアレルギーを持つ場合は、原因食品の回避が基本です。花粉症の人は、花粉飛散期に特に生のトマトを避ける、あるいは花粉症の治療をしっかり行うことで症状を軽減できる場合があります。原因花粉に対する免疫療法がPFASを予防・改善することもあり、総合的なアレルギー管理が重要です。
加熱や加工
軽度の口腔アレルギーなら、トマトを加熱したり、皮をむいたりするだけで症状が出なくなることがあります。ただし重症(LTP)患者は、加熱済みでもアナフィラキシーのリスクが残るので自己判断は禁物。必ず主治医に相談しましょう。
7.花粉症との関連:交差反応に要注意
トマトは花粉症(シラカバ、イネ科、ヨモギ、ブタクサなど)を持つ人にとって、口腔アレルギー症候群(PFAS)の原因食品として知られています。主な交差反応の仕組みは以下の通りです。
-
プロファイリン(Sol l 1):イネ科花粉(Phl p 12)やブタクサ花粉(Amb a 8)などと構造が類似し、生のトマトで口腔内のかゆみを引き起こしやすい。
-
PR-10(Sol l 4):シラカバ花粉(Bet v 1)との交差が代表例で、リンゴやニンジンなども同じタイプの症状を起こしやすい。
-
LTP(Sol l 3など):ヨモギ花粉(Art v 3)やブタクサ花粉(Amb a 6)とも部分的に交差。重症の全身性アレルギーを招く可能性がある。
花粉症の種類によって、どの分子が交差しやすいかが変わります。したがって、トマトだけでなく同系統の果物・野菜にも注意が必要です。また、ラテックスとの交差(ラテックス-フルーツ症候群)もあり、バナナやアボカドなどと一括りに反応を起こす場合があります。
おわりに
トマトアレルギーは、野菜アレルギーの中でも地中海地域で特に症例が多く、近年はアジアでも認知度が高まっています。
症状は「口の中がイガイガする」程度の軽症から、まれにアナフィラキシーを引き起こす重症型まで多岐にわたります。
背景にはIgEを介する即時型が中心ですが、花粉との交差(PFAS)やLTPアレルギーによる重症例、さらに接触性皮膚炎やFPIESなど非IgE型も一部報告されています。
参考文献
-
Włodarczyk K. et al. Tomato Allergy: Characterization of Selected Allergens and Antioxidants of Tomato – A Review
-
Thermo Fisher Scientific Allergen Encyclopedia – Tomato (f25)
-
Kondo Y. et al. Japanese Cedar Pollen–Tomato Allergy and Immunotherapy Outcomes
-
Zawodniak A. et al. Profilin and PR-10 Proteins in PFAS (Review)
-
ACAAI – Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome)
-
Zhang J. et al. Prevalence of Food Allergy in China (Meta-Analysis)
-
Pulmonology Advisor – 果物・野菜アレルギーの小児有病率 (台湾)
-
Palacin A. et al. Mugwort Pollen LTP and Cross-Reactivity
-
Sicherer S, Sampson H. Food Allergy: Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment (Review)
-
Brehler R. et al. Latex-Fruit Syndrome: IgE Cross-Reactivity Studies