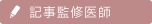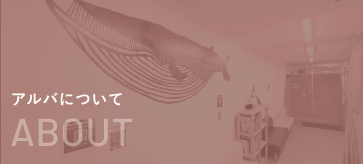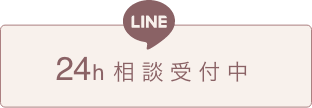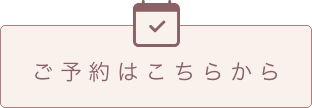エビ・カニアレルギー(小児・大人)
1) エビ・カニアレルギーとは
エビやカニの甲殻類のアレルギーは、発症年齢が比較的高く、「子どもよりも大人に多い」印象のあるアレルギーです。
そもそも、食べる頻度の違いから、カニアレルギーよりは圧倒的にエビアレルギーが多いです。
エビもしくはカニに症状があった場合には、65%の確率で合併しているとされています。
が、経験には両方がダメな人は少なく、どちらか1つだけ、合併しているのは、全体の20%程度です。
つまり、ほとんどの人が「エビだけのアレルギー」です。
また、甲殻類に関しては、採血だけでの判断は難しいです。
ダニと甲殻類はアレルギーを起こす成分が一部かぶっているので、ダニのアレルギーがあると採血するとエビ・カニの数値はは上がります。
つまり、ダニアレルギーがある場合、採血の解釈が必要で、「実際に食べてみないとわからないことも多い」とゆうことになります。
しかし、ダニもエビも採血の数値が上がっていた場合、エビの値がダニを逆転していることがあります。
通常は、ダニのほうが数値が圧倒的に高いので、この逆転の場合には採血だけで判断できます。
経験的に小児の場合には、採血で反応がなければ、エビを食べても症状がでることは基本的にありません。
しかし、大人の場合には採血の値が高ければ確定できますが、反応がなくても「アレルギーではない」とはいえません。
むしろ、エビとネコは採血の値が0.1未満と低いほうが、症状はひどくなりやすい印象です。
ひどくなるとゆうことは、救急車で運ばれる可能性があるとゆうこと。
皮膚テストでアナフィラキシーを起こすこともあります。
2)突然アナフィラキシーになる
エビ・カニアレルギーは、「突然アレルギーになる」のではなく、「軽い症状を無視していたら、突然アナフィラキシーになった」がほとんどの印象です。
エビ・カニアレルギー症状は、ほとんどが1時間以内に症状が出現します。
甲殻類アレルギーの場合、皮膚症状約80%、口腔内症状約50%、呼吸器症状30%、腹部症状17%とされていますが、アナフィラキシーを起こすことも少なくありません。
「顔面が腫れる」、「口が痒い」は、子どもの甲殻類アレルギーの特徴ですが、成人は症状がより強くでる印象です。
エビ・カニアレルギーでのアナフィラキシーは、印象的には子どもより大人のほうが圧倒的に多いです。
昨日までは無症状だったのに、ある日突然アナフィラキシーで発症する大人の小麦アレルギーと違い、甲殻類アレルギーは、エビを食べて「口がかゆい」などの小さな症状を無視していると、ある日突然アナフィラキシーになります。
救急車で搬送されてくる人が、「普段は口が痒いだけだった」と言われることが多いのも、これが理由です。
3)生のエビだけのアレルギー
以前のエビ・カニは加熱してもアレルギー成分が減ることはありませんし、さらにエビの種類によって症状に違いはありませんでした。
しかし、「生のエビだけ」に症状が出る人、「特定のエビのみ」に症状がでる人もいます。
これは多くの場合に子どもでしたが、2年ほど前からは大人も「生のエビだけ」に症状が出る人、「特定のエビのみ」に症状がでる人が出てきました。
多くの人が「生だろうと加熱しようと症状がでる」ことに変わりはありません。
また、子どもの場合には、エビそのものを食べてアレルギー症状を出しますが、大人の場合には、エビそのものではなく、スープやラーメンなどでアレルギー症状を起こすことが多いです。
子どもと大人に共通しているのは、「発症したら治らない」とゆうことです。
治療として、食べて慣らす方法も可能ですが、エビを食べ続けるより、完全除去を選ぶことが通常です。
4)貝類とエビアレルギー
関係ありませんし、合併もしないことがほとんどです。
魚介類は水産物の総称ですので、エビ・カニ(甲殻類)は一緒ではありません。
貝類、イカ、タコ、ホタテ、カキなどのアレルギー自体が珍しいので、甲殻類との合併はさらに珍しいとゆうことになります。
研究結果では、これらのイカ、タコ、ホタテ、カキなどとは、アレルギーを起こすタンパク質の成分がエビと似ている部分があるので、約20%の確率で合併するとされていますが、私の患者さんでは年に1人いるかいないかです。
「基本的に関係ない、けどアレルギー科に来る人は、たまにいます」くらいに考えた方がよろしいかと思います。
うちの娘が、フランス人の姪っ子たちから教えてもらってました。
■アレルギー治療は当院「アルバアレルギークリニック」にお任せを
アルバアレルギークリニックは、「治す」をトコトン目指しているクリニックです。
常に最新の技術がないか国内外の学会を渡り歩き、学術論文とエビデンスに基づいて「どうすればより良く治せるのか」を考え続け、より最適なアプローチ方法を提供し続ける努力をしております。
当院では、他のクリニックでは治らなかったという難治性の肌のアレルギーの患者様が遠方から来られることも多く、高い治療効果にご満足いただきご紹介いただく形でのご来院が非常に多いです。
当院のより詳しい実績については、こちらのページをご覧ください。
2023年 アトピー性皮膚炎改善率94.1% 詳しくはこちらから
また、当院ではアトピー性皮膚炎が改善された方からの多くのご要望をいただき、肌の弱い方の医療脱毛やニキビ治療などアトピー性皮膚炎が改善された後の治療も行っております。
自由診療で行っておりますので、ご興味のある方は診察室にて一言お声かけください。
アレルギー治療の予約や自費診療のご予約をご希望の方はこちらをクリック
【参考文献】
1: 中島 陽一、他.日常診療で判断に迷う魚・甲殻類・魚卵・果物などのアレルギーの診断・日小ア誌 2019;33:47-5
2: Suttipong Ittiporn, etal. Natural resolution of non-anaphylactic shrimp allergy
in patients diagnosed 10 years earlier by oral food challenge. Asian Pac J Allergy Immunol 2021;39:249-257.
3: 松井 照明,他. 甲殻類・貝類. 日小ア誌 2020;34:408-418
7: G. Celi, etal. House dust mite allergy and shrimp allergy: a complex interaction. Eur Ann Allergy Clin Immunol Vol 52, N.5, 205-209, 2020.
8: 症例を通して学ぶ 年代別食物アレルギーのすべて