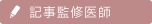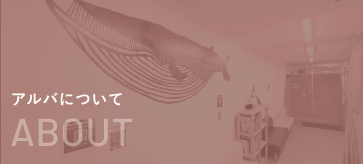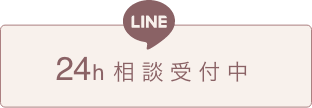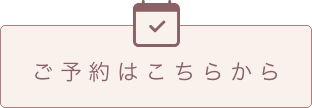果物・野菜アレルギー:一覧(2025)

北海道での果物・野菜アレルギー
北海道では果物・野菜アレルギーが花粉症と関連して起こるケースが多く、花粉症になるとその30~50%の人が果物・野菜アレルギーを発症すると言われています。
| 花粉 | 反応を起こしやすい果物 | 反応を起こしやすい野菜 |
|---|---|---|
| シラカバ・ハンノキ(カバノキ科)、マタタビ科、セリ科、ナス科 | リンゴ、モモ、ナシ、サクランボ、イチゴ、ウメ、ビワ、キウイ、マンゴー、アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、ブドウ、柿 | ニンジン、セロリ、ジャガイモ、トマト、ナス |
| カモガヤ、オオアワガエリ(イネ科)、ウリ科、ナス科、バショウ科、ミカン科、セリ科 | メロン、スイカ、オレンジ、バナナ、キウイ、みかん、キンカン、シークワーサー、グレープフルーツ、ブドウ | トマト、ジャガイモ、セロリ、トウモロコシ、ひよこ豆、レタス、ナス |
| ブタクサ、ヨモギ(キク科)、ウリ科、セリ科、バショウ科、マタタビ科、ムクロジ科、アブラナ科 | メロン、スイカ、バナナ、マンゴー、キウイ、ライチ | セロリ、ニンジン、コリアンダー(パクチー)、クミン、キャベツ、ブロッコリーキュウリ、ズッキーニ、キャベツ、ブロッコリー、ごぼう、 |
| スギ(ヒノキ科) | 特になし | トマト |
| その他 | カキ:カキノキ科、ブドウ:ブドウ科、ゴボウ:キク科、ナガイモ、ヤマイモ:ヤマノイモ科、タマネギ、ニ ンニク:ヒガンバナ科(ユリ科)、クリ:ブナ科、アボガド:クスノキ科、マンゴー: ウルシ科、ホウレンソ ウ:ヒユ科、大豆:マメ科、レタス:キク科 |
|
日本の中でも北海道はシラカバの飛散量が年によって大きく変動し、その差は200倍にも及ぶとの報告があります。
こうした地域的特性によって、花粉症自体を自覚しないまま果物・野菜アレルギーの症状が出てしまう場合も多くあります。
スギ花粉症と違い、花粉が多く飛んだ年や飛散量が非常に多い日のみ症状が出るため、ご本人が気づきにくいのです。
果物・野菜アレルギーと関連する代表的な花粉としては、4月頃から飛散するシラカバ、夏のイネ科、秋のヨモギが挙げられます。
とりわけ北海道ではシラカバが主な原因とされていますが、近年は本州を含めさまざまな地域でブナやコナラ、ヨモギなどの花粉症が増加している印象があり、今後はそれらと果物・野菜アレルギーの関連が広い地域で見られるようになるかもしれません。
さらに、ブナは土地に水を保つ力が強いことから、水源の涵養などを目的にスギからブナへの植え替えが進められているようで、その結果、ブナによる花粉症の症状が全国的に増える可能性も示唆されています。
果物・野菜アレルギーの種類
果物
| 多い順 | 小児 | 成人 |
|---|---|---|
| 1 | リンゴ | リンゴ |
| 2 | モモ | モモ |
| 3 | サクランボ | サクランボ |
| 4 | イチゴ | ナシ |
| 5 | ナシ | キウイ |
| 6 | パイン | メロン |
| 7 | バナナ | プラム |
| 8 | プラム、 キウイ、メロン、スイカ | スイカ |
| 9 | ミカン | イチゴ |
| 10 | カキ | バナナ |
野菜
| 多い順 | 小児 | 成人 |
|---|---|---|
| 1 | 大豆 | 大豆 |
| 2 | ナス | ナス |
| 3 | トマト | トマト |
| 4 | ジャガイモ、キュウリアボカド、セロリ、長いも、長ネギ | アボカド |
| 5 | 山芋、ニンジン、里芋、キャベツ、ごぼう、サツマイモ、玉ねぎ、ほうれん草、ニンニク、ズッキーニ、アスパラ、ショウガ | ジャガイモ |
一般的には花粉症を発症した後、数年かけて果物・野菜アレルギーに移行していきます。
花粉・野菜・果物アレルギーは全て同じ機序で起きるわけではありませんが、総称して「花粉・食物アレルギー症候群(PFAS)」と呼ばれ、海外の研究でもこの用語が一般的に使われています。
大まかには、花粉による感作がきっかけとなり、その花粉と似た構造をもつ果物や野菜の抗原に反応することでアレルギー症状を起こすメカニズムです。
具体的な対応は、カバノキ科(シラカバ、ハンノキ)とリンゴやナシ、モモなどバラ科の果物、またはイネ科とメロン、スイカなどウリ科の果物というように、花粉の種類ごとによく知られた組合せがいくつも存在します。
ただし、「この花粉があるから必ずこの果物にアレルギーが出る」というわけではなく、発症リスクを高める可能性がある程度にとどまるのが実情です。
稀ではありますが花粉症とほぼ同時期に果物・野菜アレルギーを発症する人もおり、研究や症例報告によっては花粉症歴が短くても果物・野菜アレルギーが発生すると言われており、花粉症がひどければ果物野菜アレルギーになる訳ではありません。
また果物・野菜アレルギーは一度発症すると、最初の1年で食べられない果物が急速に増えます。
発症後は2~3年かけて徐々に増えるケースが多いですが、大多数はその最初の段階でどの果物・野菜がダメになるかが決まるという見解もあります。
北海道では果物・野菜アレルギーの頻度が高い食材としてバラ科(リンゴ、ナシ、モモ、サクランボなど)が有名です。
以前はリンゴ、モモ、ナシのみのケースが多い印象でしたが、最近はイチゴ、サクランボもかなり増えている印象です。
ただし、非バラ科の果物でも頻度としては決して無視できず、キウイやマンゴーなど他の分類に属する果物がアレルゲンとなる例もあります。
北海道で特徴的なのは野菜に対するアレルギーが多いことです。
本州ではトマト以外の野菜アレルギーが比較的珍しいとされますが、北海道ではかぼちゃ、唐辛子、ごぼう、セリ、人参、キャベツなど、あまり聞き慣れない野菜アレルギーを持つ方が少なくありません。
海外文献でも、セリ科(セロリ、ニンジン、パクチーなど)やアブラナ科(キャベツ、ブロッコリー等)に対する報告が一定数あり、とくにヨーロッパの一部ではニンジンアレルギーが比較的よく知られています。
野菜アレルギーの多くは高齢者に多いという印象が従来はありましたが、最近は花粉症の低年齢化がすすんでおり、小児でも野菜アレルギーを発症するリスクが無視できなくなってきています。
5~6年前まではバラ科の果物アレルギーを30代くらいまでに発症するのが一般的で、それ以上の年齢で新たにバラ科アレルギーが生じるケースは少なかったです。
しかし、ここ数年は50~60代でも発症報告が増加している傾向があります。この変化が何によるものかは明確ではありませんが、花粉症自体の増加やスギ以外の花粉の影響など、複合的な要因が考えられます。
海外の調査によると、PFAS発症の背景には遺伝的要因だけでなく、居住地や花粉暴露の環境要因が強く影響することが指摘されています。
たとえばシラカバ花粉が多い北欧やロシアの一部では、バラ科果物へのアレルギーが高率で認められる一方、地中海地域ではヨモギ花粉が多いこともあり、セロリやニンジンなどのセリ科野菜アレルギーの報告数が比較的多いというデータがあります。
こうした地域差は日本国内でも顕在化しており、地域の花粉飛散状況によって果物・野菜アレルギーの傾向が変わってくるのは自然なことといえるでしょう。
採血結果
果物>野菜でアレルギーになりやすく、一般的によく食べられる果物がアレルギーになります。
「自分がどの果物・野菜で症状が出るか」を正確に把握するには、採血検査(特異的IgE)なども用いながら、実際に食べたときの反応や既往歴を総合的に判断する必要があります。
しかし、果物・野菜アレルギーにおいては採血は医学的基礎知識がないと判断するのは無理で、検査結果と症状との間に乖離が生じるケースも多いです。
特に、「食べて症状がないにもかかわらず採血では陽性が出る」「採血で陰性だが実際に食べてみると症状が出る」といった問題が時々存在します。
そのため、アレルギーに詳しい医師が患者さんの症状と検査結果を合わせて評価することが重要です。
北海道の花粉症と採血結果
果物野菜アレルギーの症状
| 症状 | アナフィラキシーの可能性 | |
| リンゴ、モモなどよくあるやつ | 口腔内掻痒が多い | 人によりある |
| ニンジン、ライチ、セリなど珍しいやつ | 倦怠感、鼻血、頭痛など | 多い |
| クミンやコリアンダーなどのスパイス | 呼吸苦、全身蕁麻疹など | 非常に多い |
果物・野菜アレルギーは、種類によって発症する年齢が大体決まっています。
- 乳児期:バナナ、キウイ、大豆、ジャガイモ
- 1歳~5歳:キウイ
- 5歳以上:リンゴ、モモ、ナシ、サクランボ、イチゴ、パインなど
- 7歳以上:上記に加えて柿、トマト、ジャガイモ、ネギな、メロン、スイカど
- 13歳以上:上記に加えて大豆、トマト、バナナなど
- 60歳以上くらい:ニンジン、セリ、キャベツ、サツマイモ、ダイコンなど
花粉症がある方は果物や野菜を食べるときに口の中の異常感覚や腫れ、咽頭のイガイガ感などに注意する必要があります。
リンゴ、モモ、ナシサクランボなどよく知られたものは口の中が痒いだけのことが多いですが、呼吸苦、全身蕁麻疹などの症状もあります。
一方で、ライチやセリ、トウガラシなどの珍しい果物・野菜は、倦怠感、鼻出血、頭痛など
もしこうした症状が出たら、そのときの状況(食べたもの、料理方法、同時に摂取した飲み物の有無など)をメモしておくと、医療機関で相談するときに役立ちます。また、「最初はリンゴやナシ、サクランボなどのバラ科の果物だけだったのに、いずれキウイやマンゴーなど非バラ科でも症状が出るようになった」という経過をたどる方もいらっしゃいます。
アナフィラキシー
アレルギー症状として多いのは、口やのどの痒み(口腔内症状)ですが、咳や呼吸苦、腹痛、嘔吐、さらにはアナフィラキシーを起こす場合もあります。
本人の体調や食べる量、調理法によっても大きく変化し、加熱で症状が起きにくくなるケースがある一方、まったく変わらない場合もあるため、一概に「加熱すれば大丈夫」とは言い切れません。
特に注意が必要なのは、アルコール飲料を混ぜたフルーツカクテルや野菜ジュースなど、液体の形で一気に体内に取り込むケースです。
固形物であれば、途中で「口やのどがかゆい」というサインに気づいて摂取を中断できることもありますが、飲み物の場合は短時間で大量に摂取してしまうため、気づいたときにはすでに症状が出始めており救急搬送されるリスクが高いです。
私は以前から学会で発表していますが、救急搬送されるほどの重症例の約9割が飲み物をきっかけとするアレルギー反応でした。
成人食物アレルギー患者の大多数がアナフィラキシーを経験するとの報告もあります。
これは成人の食物アレルギー全般に言えることです。
トルコの成人食物アレルギー患者33例の研究では、72.7%がアナフィラキシーを呈し、緊急治療としてエピネフリン(アドレナリン)注射が必要になった例も約3割に上りました。
アナフィラキシーでは皮膚・呼吸器・消化器の複数臓器症状が同時に現れ、成人では特に血圧低下や意識障害などの循環器症状の頻度が高いことが知られています。
小児の食物アナフィラキシーでは嘔吐など消化器症状が目立つのに対し、成人ではショック(循環不全)を来す割合が高く(成人36% vs 小児16%)、命に関わる重篤な状態に陥りやすい傾向があります。以上のように、成人の卵アレルギーでは全身性の激しい反応が起こり得るため、エピペンなどの緊急対処法の携帯が推奨されます。
最後に
果物・野菜アレルギーを抱える人の大半はバラ科に限られますが、高齢者ほどバラ科以外にも症状が及ぶ傾向が見られ、この傾向は小児にも広がっています。
これには加齢とともに花粉感作が複数重なることや、免疫システムの変化など、いくつかの要因が考えられます。
以前は若年成人までにしか発症しなかったと思われていたバラ科果物アレルギーが、中高年以降でも発症する例が増えているという臨床報告も無視できません。
今後は花粉症の有病率増加や花粉飛散時期の変動なども相まって、より幅広い年齢層が多種多様な果物や野菜に対してアレルギーを発症する可能性があると考えられます。
このように、PFASは花粉症と果物・野菜アレルギーが連動する複雑な病態であり、疾患の起源や発症リスク、重症度の評価など、多角的な視点が必要になります。
特に北海道のようにシラカバやイネ科の花粉が多い地域では、本州と異なるパターンで野菜アレルギーが見られるため、「果物・野菜アレルギーは珍しい」と思い込まず、少しでも疑わしい症状があれば早めに受診を検討することをお勧めします。
【参考文献】
福家 辰樹. 日小ア誌 2020;34:602-611.
近藤 康人. 日小ア誌 2022;36:81-85.
佐藤さくら, 他. 日小ア誌 2022;36:14-20
山田 伸治, 他. 日小ア誌 2015;29:685-690.
村上 至孝, 他. 日小ア誌 2020;34:525-529.